2023年4月26日(水)から29日(土)までの4日間にわたり、台湾・台北にて第38回世界獣医会議(World Veterinary Association Congress、WVAC)が開催された。本会は世界獣医学協会(WVA)が主催する年次大会であり、前回の第37回は昨年、2022年にアラブ首長国連邦のアブダビで開催された。今回も臨床獣医学、公衆衛生、動物福祉などの小動物にかかわる専門分野のほか、産業動物のテーマも含まれるプログラムが組まれた。
MRTの最寄駅から直通で会場に入ると、4階に展示会場、7階に9つの講演会場が用意され、過去のMVM本誌に登場しているDouglas DeBoer先生、Philip Fox先生をはじめ、日本からも石田卓夫先生ほか複数の日本の先生による講演が組まれていた。ポスターセッションでも日本の先生方による発表が見受けられた。参加者も世界会議のため、多くの国々から参加者が集まり、最新情報を共有しあう場所となっていた。
展示会場では、90以上の企業がブースを出展、世界的に有名な企業の台湾法人が主に出店していたが、日本から直接ブースを出す企業もあり、日本と台湾の距離の近さが感じられた。また、台湾で広く展開している動物病院がブースを出展していた。台湾は日本における九州と面積(約36,000平方km)も動物病院数(1,300~1600件)も近い。日本と台湾がお互いに協力し合い、高め合う土壌がさらに深まっているように感じられた。

展示会場の様子

セミナーの様子









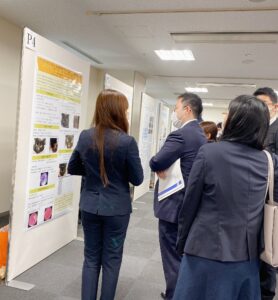




 東北地区大会
東北地区大会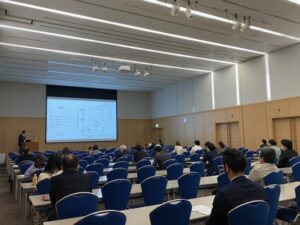
 九州地区大会
九州地区大会
 北海道地区大会
北海道地区大会







