1月22日(日)、都市センターホテル(東京都)にて、「東京VMAT」立ち上げに伴い任命式が開催された。
VMAT(Veterinary Medical Assistance Team;災害時獣医療支援チーム)は、災害時に被災地における獣医療支援などを行うために、専門的な教育をうけた獣医師を主体とした獣医療チームである。主な活動内容は、被災地の調査、被災地における連絡体制の確立、現地動物病院の業務再開に向けた支援、情報の収集と共有、災害救助犬の治療などを行う。
日本では2011年の東日本大震災の経験をふまえ、2012年に日本ではじめて、福岡県獣医師会が「福岡VMAT」を組織。その後、複数の地方獣医師会がVMATを結成している。
この度、(公社)東京都獣医師会(以下、本会)は2023年1月22日にVMATを組織し、「東京VMAT」の第一期隊員として18人を任命した。今後は都内で災害が発生した場合、被災地域支部からの要請および本会危機管理室長(災害対策本部設置時には災害対策本部長)の判断により、活動可能な東京VMAT隊員のなかから派遣隊を組織し必要な活動を行うこととなる。また、東京都以外の道府県の災害発生時は、当該地方会および(公社)日本獣医師会からの要請により、本会の危機管理室長の判断にて同様の活動を行うことができる。
「東京VMAT」は本会の危機管理室が定めるVMAT研修プログラムの修了者により構成される。このプログラムは、本会会員または会員が開設する動物診療施設勤務者などが受講できるが、当面の間は会員獣医師に限られる。研修プログラム修了者には「東京VMAT隊員証」が授与され隊員名簿に登録される。所定の研修を修了した者に「東京VMAT隊員証」を授与され隊員名簿に登録される。
「災害時は自助、共助、公助、そして互助の精神が大切です。お互いに助け合わなければ。」と上野会長。万が一の災害発生に備え、獣医師会全体として日頃からの協力体制づくりが重要であることを再認識する任命式であった。

上野弘道先生(危機管理室長/(公社)東京都獣医師会 会長)。
「互助」の精神が大切であると語る

藤本順介先生(危機管理室情報統括/東京都獣医師会 武蔵野三鷹支部)。
本会の災害対応の特徴や東京都の被災想定など、東京VMATをとりまく
最新の状況を解説された

任命式の様子。所定の研修を修了した有資格者には
「東京VMAT任命書」が授与され、東京VMAT隊員名簿に登録される

任命式にて。「東京VMAT」第一期隊員の方々とブロック長の羽太真由美(町田支部)、伊東秀行(葛飾支部)。
第一期隊員は、安部浩之(城北支部)、石森斉子(江東支部)、磯 洋一(足立支部)、入交眞巳(動物薬事支部)、植松一良(多摩西支部)、河合博明(八王子支部)、木村章子(多摩西支部)、木村譲(多摩東支部)、斎藤朋子(八王子支部)、斉藤勝之(新宿支部)、清野光司(多摩西支部)、髙橋恒彦(新宿支部)、谷川久仁(中野支部)、中川清志(北多摩支部)、中島 豪(多摩東支部)、名川一史(練馬支部)、藤本順介(武蔵野三鷹支部)、安田辰巳(江戸川支部)※敬称略



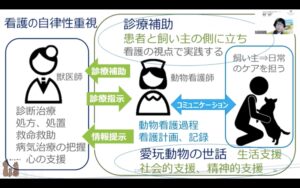












-300x225.jpg)
