2025年10月31日(金)から11月2日(日)の3日間にわたり、韓国・大邱(テグ)にて第13回アジア小動物獣医師会大会(FASAVA〈Federation of Asian Small Animal Veterinary Associations〉2025)が開催された。前回2024年7月のクアラルンプール大会から1年、今回は10月末の開催となり、日本をはじめアジア各国、欧米、オセアニア、アフリカなど全世界33ヵ国から4,500名以上の参加者が集まった。
大邱は、韓国第3の都市といわれ、韓国唯一の都市型モノレールがあり、交通量も比較的多い印象である。会場のEXCO(大邱展示コンベンションセンター)は、大邱市街の北側に位置し、2001年に開館した複合展示施設である。ちなみに日本との時差はない。
講義は最大10セミナーが並行して開かれ、メインプログラムとして、救急、整形外科、行動、猫、軟部外科、内科、循環器、眼、皮膚、神経、臨床病理、腫瘍など70以上のプログラムが用意された。日本からは浅野和之先生(日本大学)、新居康行先生(JASMINEどうぶつ総合医療センター)、金園晨一先生、佐藤雅彦先生(ともにどうぶつの総合病院)、細谷謙次先生(北海道大学)、是枝哲彰先生(JARVISどうぶつ医療センター Tokyo)の6名の講演が行われた。また、現在サーカス動物病院に所属するYun-Hsia Hsiao先生も登壇した。
加えて、2日目と最終日には、「Vet Nurse(Korean)」として計12コマが設けられ、日本からは最終日に大熊摩耶氏(愛玩動物看護師、日本獣医生命科学大学)」の講演が行われた。
●初日:肌寒くも気持ちのよい朝を迎え、オープニングセレモニーがスタート。韓国の伝統と革新をイメージしたダンスのあと、FASAVA会長である石田卓夫先生(JBVP名誉会長)他多くの来賓の挨拶が行われた。その後、現WSAVA会長のJim Berry先生の基調講演「The Intersection of Welfare and pain management in Veterinary Medicine(獣医学における福祉と疼痛管理の交差点)」が行われ、アニマルウェルフェア向上のための動物の痛みを見逃さないヒントを、エビデンスやガイドラインを元に解説された。午後のレクチャーのあと、ウェルカムレセプションでは、華やかなショーや来賓挨拶、スポンサーへの表彰などが行われた。会場には、明日からの英気を養うために多くの参加者が集まり、懇親を図った。
●2日目:大邱から約60km海側にある韓国・慶州でのアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議が最終日を迎えるなか、FASAVAでは2日目のプログラムがスタートした。日本からの講演としては、午前に浅野先生の「Surgery for adrenal tumors(副腎腫瘍の外科手技)」「Surgery for liver tumors(肝臓腫瘍の外科手技)」、Yun-Hsia Hsiao先生の「New Horizons in Therapy:Managing CAD through pharmacological approaches」(治療における新しい地平線:薬理学的アプローチによるCADの管理)」、新居先生の「Canine Mitral Valve Repair(MVR):From Indications to Innovations(犬の僧帽弁修復〈MVR〉:兆しから革新へ)」が行われた。どの講演にも多くの聴講者が参加していたが、とくに浅野先生の講演には立ち見がでるほどの盛況ぶりであった。
午後には、金園先生の「Approach to Vestibular Dysfunction(前庭機能障害へのアプローチ)」「Canine Acute Intervertebral Disc Disease:True or False(犬の急性椎間板疾患)」「How to anticipate elevation of the intracranial pressure prior to MRI(MRI前に頭蓋内圧の上昇を予測する方法)」、佐藤先生の「〜Recent advances in feline medicine〜 Updates on DM,FIP and CKD(〜最近のネコ医学の進歩〜DM、FIP、CKDに関する最新情報)」が行われ、こちらも多くの聴講者であふれかえった。
この日の夜にはコングレスディナーが行われ、石田会長らがプレゼンターを務めた表彰式やダンスや歌などのショー、そしてコース料理などを参加者は楽しんだ。
●最終日:日本の先生の講演としては午前に細谷先生の「From 10-year experience of IG/IMRT:Have we really advanced to the next stage? How far have we come?(画像誘導/強度変調放射線治療の10年の経験から:私たちは本当に次の段階にすすんだのか、どこまで来たのか」、午後に是枝先生の「Total Hip Replacement in dogs and cats(犬猫の股関節全置換術)」「Surgery in Motion:Lectures and Videos of FHO and THR(動画による手術講義:FHOとTHRについて)」、大熊氏の「Veterinary Nurses for Companion Animal,Now a Nationally Certified License(愛玩動物看護師の国家資格化の現状)」「Hospitalization Nursing Care and Nursing Documentation Process(Animal Nursing Records)(入院看護ケアと動物看護記録)」が行われた。
クロージングセレモニーでは、ポスターセッションのアワード表彰ほか、次回FASAVA2026が台湾・台北にて2026年10月31日(土)〜11月2日(月)に開催されることが発表された。
展示会場には、ヒルズ社をはじめ、120に及ぶ企業および関連団体が集まった。日本企業関連のブースも見受けられ、日本と韓国をはじめとするアジア各国との距離がますます近づいている印象を受けた。また、一部の会場では、AIによるリアルタイム翻訳が導入され、参加者は手持ちのスマートフォン等でQRコードを読み取れば英語、韓国語、日本語が飛び交うディスカッションや質疑応答なども瞬時に理解でき、これからの学会の一つのインフラとして非常に効果的であると感じられた。
アジアの小動物医療の世界で、日本は日本ならではの強みを維持および発揮していけるのか。日本はアジアからの期待に応えられるのか。その際に重要なのは「情報」であり、その取捨選択の判断材料を多くの方が入手できる環境の構築が鍵になると思われる。本大会のすべての参加者は、貴重な「情報」を多く得たにちがいない。
Pick Up:ポスターセッション
今大会では、ポスターが約200題集まり、日本からも多くの先生方が発表された。そのうち、6題は東京都獣医師会会員による報告であり、池田人司先生(オールハート動物リファーラルセンター)と渡辺靖子先生(自由が丘動物医療センター)がアワードを受賞した。この2名を含む発表者会員6名には東京都獣医師会から渡航費や滞在費などの補助金が支払われた。来年以降も継続して支援するとのことで、アジアの獣医療関係者とのコンタクト、また日本の学会とは異なる熱気を感じられる絶好の機会として、次回の台北大会にてポスター発表を検討されてはいかがだろうか(詳しくは東京都獣医師会まで)。


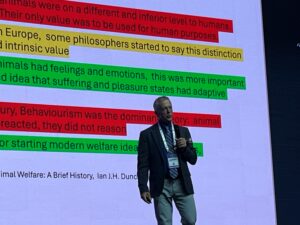


学会・セミナーレポート
- 2026年2月 (2)
- 2026年1月 (2)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (7)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (6)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (7)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (4)
- 2025年3月 (7)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (5)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (10)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (5)
- 2024年7月 (4)
- 2024年6月 (3)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (4)
- 2024年3月 (2)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (6)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (5)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (7)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (6)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (3)
第13回アジア小動物獣医師会大会(FASAVA2025)
大邱(テグ)大会 開催される
2025/10/31
第15回動物看護大会 開催される
2025/10/27
2025年10月26日(日)、日本獣医生命科学大学E棟(東京都・武蔵野市)で、(一社)日本愛玩動物看護師会(JVNA、会長 横田淳子氏)主催、農林水産省、環境省後援による、第15回動物看護大会が開催された。日本動物看護職協会から日本愛玩動物看護師会と名称変更してからのはじめての開催となる。
今年のテーマである「明日からのケアが変わる! ライフステージ別動物看護」のもと、教育セミナーでは、森 勇人先生(TRVA動物医療センター)が「そのトリアージ、“なんとなく”で終わらせない!-気づき・考え・動ける愛玩動物看護師になるために-」、富永良子氏(nobita)が「周産期ケア~自宅主産をどうサポートするか」を講演した。多くの聴講者は日々の診療のなかで判断の基準となる新たな知識を得られたと思われる。
シンポジウムは、シニアケア「動物病院もその先も」で、中村陽子氏(ペットケアホーム フズル)が「動物リハビリテーション」、安部里梅氏(ペットケアホーム リュッカ)が「どうぶつ介護総合施設」について講演した。2名とも起業した愛玩動物看護師であり、それぞれの現場での実例に基づく看護やシニア期の動物と暮らす飼育者の心情について解説された。シンポジウムの最後に、ファシリテーターの横田会長およびフロアの聴講者を交えたディスカッションがあり、有意義な意見交換が行われた。
本年も採血実習セミナーが開催され、参加者はシミュレーターを用いた採血を講師のアドバイスを受けて行った。
いなばペットフード(株)企業セミナーとして、谷口 優先生(国立環境研究所)の「伴侶動物との暮らしが人や社会保障にもたらす効果」の講演が実施された。犬と暮らすことで要介護認知症発生リスクが低下すること、伴侶動物と暮らす方の月額介護費用が抑えられることなど、動物がもつ社会の有益性をエビデンスとともに解説された(MVM2026年1月号で同内容の記事を掲載)。
動物看護研究では9題の口頭演題があり、そのなかから中島佳代子氏(とがさき動物病院)「後躯麻痺での排尿障害を呈する犬に対する入院中の床材の検討」がヒルズアワードを、遠藤さくら氏(ALL動物病院グループ)「入院動物に対する適切な栄養管理体制の構築」がJVNA優秀賞を受賞した。
閉会式では、近江俊徳先生(日本獣医生命科学大学)が「多彩で充実した内容のプログラムが展開され、どの講演も愛玩動物看護師としての専門性をさらに高めていこうという強い使命感と情熱を感じることができた。動物看護研究では日々の業務のなかから確かな実践を重ねていることがわかった。後に続く方もこれらの研究を参考にさらによりよい研究を行っていただきたい」と総評した。

講演の様子
第46回動物臨床医学会年次大会 開催される
2025/10/20
2025年10月18日(土)、19日(日)にグランキューブ大阪にて、第46回動物臨床医学会年次大会が開催された。
プログラムとして、ベーシック・ステップアップ・アドバンスの各セミナー、パネルディスカッション、動物病院スタッフセミナー、各研究会のシンポジウムとセミナー、産業動物分科会のプログラム、企業主催のランチョンセミナー、一般口演、症例検討、ポスターセッション、スタッフ口頭発表、市民セミナー、そして本学会が2025年から新たに設立した認定愛玩動物看護師制度の認定講習対象セミナーなど、多くの講演が実施された。各会場には獣医師だけでなく愛玩動物看護師や学生、動物病院スタッフなどが聴講へ集まり大変盛況であった。また今大会では展示会場でも講演スペースが設けられ、参加者が各企業の展示ブースへ足を運びやすい工夫がされていることも印象的であった。
初日には昨年の一般口演から選考された学会長賞および各文科会アワードの授与が行われ、学会長賞として「犬のポリニューロパチーの臨床的特徴と予後因子」の演題で発表を行った長谷川裕基先生(KyotoAR 動物高度医療センター)が表彰された。夜には展示会場にて参加費無料のウェルカムパーティーが開催され、こちらにも多くの参加者が集まり、乾杯の前に、ご逝去された前理事長の山根義久先生への黙祷が捧げられた。
全体としては学生や愛玩動物看護師の参加者が増えており、熱心に聴講する姿や情報を集めようとする姿勢が非常に印象的であった。本学会の今後の展開が期待される。
次回動物臨床医学会第47回年次大会は、2026年10月24日(土)、25日(日)に同じくグランキューブ大阪にて開催予定。

2日目の3階展示会場横でのセミナーの様子
2025年10月18日(土)、同年9月24日に新しく開設された大阪公立大学森之宮キャンパス(大阪府大阪市)にて開設記念シンポジウムとして、「Zoobiquity Symposium-ワンヘルスが導く医療と獣医療の新時代-」が開催された。
プログラムはすべて同時通訳つきで実施され、午前中は「さまざまな動物の心臓病態生理学-生息環境による心臓形態の変化―」(鯉江 洋先生、日本大学)、「猫尿臭はヒトにおける高コルステロール血症を防ぐ新たな手がかりを提供する」(宮崎雅雄先生、岩手大学)、「獣医学における汎動物学の実践―解剖学教育と腎臓研究の現場から-」(市居 修先生、北海道大学)の講演が実施された。
ランチョンセミナー「Zoobiquityと幹細胞:再生医療の未来を探る」(塚本雅也先生、大阪公立大学)の後、午後最初のプログラムでは基調講演としてカルフォルニア大学のDr. Barbara Natterson-Horowitzによる「The Future of Medicine: Human and Animal Health in the 21sr Centyry」が実施された。当初実施予定であった2020年からコロナ禍を経て、ようやくかなったDr. Horowitzの講演であった。
続くパネルディスカッションは2部構成で展開された。第一部は「One Healthの将来を担う若手の育成について」をテーマに、「アジアの取り組み」(Dr. Juhyung Hur、アジア獣医師連合会長)、「コロラド州立大学の取り組み」(Dr. Tracey Goldstein、コロラド州立大学One Healthセンター所長)、「北海道大学の取り組み」(寳金清博先生、北海道大学総長)、「帯広畜産大学の取り組み」(古林与志安先生、帯広畜産大学副学長)、「大阪公立大学獣医学部のOne Healthへの取り組み」(山岸則夫先生、大阪公立大学獣医学研究科研究科長)が講演された。
第二部は「学生が考えるOne Healthの将来」をテーマに、「シバヤギを活用した除草活動」(奥薗翔太さん・小田切 茜さん・片岡沙矢さん・栗本みのりさん・黒田いちごさん・前田一樹さん、大阪府農芸高等学校 資源動物科 ふれあい動物専攻)、「獣医学生が描く、教育とAIからはじまるOne Healthの未来」(坂口実優さん、大阪府立大学 生命環境科学域 獣医学類)、「医学部と獣医学部における「One Health」と「Zoobiquity」に関する意識調査」(鵜澤 悠さん・政田佳祐さん・市原明子さん・弁野 遼さん、大阪公立大学獣医学部)、「One Healthの実現に向けて:小学生への“いのちの授業”と獣医再生医療研究」(杉崎晧子さん、大阪公立大学 大学院獣医学研究科)の発表がされた。
Zoobiquityをとりまく日本、アジアやアメリカでの現状を学び、教育の重要性に対する認識を高める1日となった。
なお本シンポジウムは(一財)J-HANBSと北海道大学との共催であり、とくにJ-HANBS 理事長の加藤 元先生は、2018年から本シンポジウムの開催に向けて尽力してこられた。コロナ禍を経てようやく開催された本シンポジウムが、「人、動物、自然環境」の3つの要素を一体としてとらえる「Zoobiquity」概念を普及する牽引役として、J-HANBSをはじめ各教育機関、研究機関の活躍がますます期待される。

コロナ禍を経てようやくシンポジウムの開催を実現。その喜びを分かち合うDr. Horowitzと加藤 元先生。加藤先生は2018年に渡米し、Dr. Horowitzに日本での講演を依頼していた。シンポジウムは当初2020年10月の開催が決まっていたが、同年3月からのコロナ禍により延期を余儀なくされ、先行きがみえない状況下、一旦中止にみまわれた。しかし昨年2024年から再度企画を立て直してのプロジェクトがスタートし、今回のシンポジウム開催に至った

Dr. Horowitz先生の講演の様子

会場の様子。写真は本シンポジウム共催の北海道大学総長 賽金清博先生の講演

大阪公立大学獣医学部附属獣医臨床センターは米国動物病院協会(AAHA)による国際認定を取得。本学獣医学研究科科長 山岸則夫先生(右)と、米国動物病院協会(AAHA)日本支部代表 松沼謙一氏(左)

参加者全員で(一財)J-HANBS理事長加藤 元先生を囲んで
2025年10月14日(火)、衆議院第二議員会館(東京都千代田区)でNPO法人 人と動物の共生センターによる「生活困窮者のペット飼育問題の解決に向けて」セミナーが実施された。
本セミナーは、「国内で多発する〈多頭飼育崩壊〉等の問題の背景には、飼育者の精神障害・経済的因窮等の問題が隠れている」「〈動物の問題〉ととらえられやすいが、〈人の困窮・人の福祉の問題〉が、動物の問題という形で表出したもの」「解決には、動物福祉と社会福祉、民間と行政の横断的な協力が必要だが、まだまだ認知されていない。日本全体の問題として取り上げ、関係者と情報共有し、解決への糸口を探りたい」という3つの趣旨をもとに実施された。
本センターの理事長を務める奥田順之先生により生活困窮者ペット飼育の課題や、岐阜市内19ヵ所の地域包括支援センター所属の職員の協力によるアンケート結果、国の政策と現実などが紹介された。続いて支援現場の声として、「人と動物の福祉の繋~高齢社会の中、顕在化してくるペットと高齢者の問題とは~」(森 茂樹氏、かわさき高齢者とペットの問題研究会)の報告が行われた。生活困窮世帯の猫の飼育をメイン事業とする「人もねこも一緒プロジェクト」小池英梨子氏からは2017年から現在までの対応案件の詳細についての報告が行われた。「生活困窮ペット飼育者支援に関する院内勉強会」(亀山嘉代氏、NPO法人ねりまねこ)の発表では東京都練馬区での活動状況が報告され、また医療の立場から「在宅療養患者におけるペット問題」(白神真乃先生、医療法人かがやき総合在宅医療クリニック、「とこのこ」代表)が報告された。
問題の解決には、飼い主への高齢者が健常な時期に早めに相談できる窓口、教育などの早期介入や、個人情報との兼ね合い、行政との連携やドネーションの重要性が紹介された。
本セミナーには100名近い参加者が集った。動物の愛護及び管理に関する法律の策定にかかわった議員も臨席し、問題解決に向けた情報共有や提案を呼びかけた。
“行政”、“ボランティア”、“飼い主と犬や猫”の問題解決のハブ(中継地点)を行政あるいは公的機関におくことで解決できる事案は少なくないのではと、本センター理事長の奥田順之先生はいう。
福祉問題のからんだペットの飼育問題の解決に向けて、本センターの牽引がますます期待される。
本センターの詳細は下記より。
https://human-animal.jp/

奥田順之先生の講演の様子

パネルディスカッションの様子・左から森 茂樹氏、白神真乃先生、小池英梨子氏、亀山嘉代氏、ファシリテータを務める奥田順之先生
第28回日本獣医療倫理研究会(JAMLAS) 開催される
2025/10/5
2025年10月5日(日)、京王プラザホテル(東京都・新宿区)にて第28回日本獣医療倫理研究会(JAMLAS)が開催された。
今回のテーマは、「リクルートトラブルを研究する」。本研究会会長の白永伸行先生(シラナガ動物病院)の挨拶からはじまり、本研究会顧問弁護士の春日秀文先生(春日法律事務所)からは「今年の動物医療事件裁判例」と題し、ある動物病院で実際にあった判例をもとに、どの部分が争点となったのかを示し、これからの日々の臨床現場に活用できる内容を解説した。
「失敗から学ぶ採用戦略-人材紹介を利用して」では、平林弘行先生(さくら動物病院)が、「事例紹介」では、弓削田直子先生(VCAJペットクリニックアニホス)が、「東京都獣医師会でのリクルートトラブル防止の取り組み」では、宮下めぐみ先生(エルザどうぶつ福祉病院/東京都獣医師会)が、それぞれの立場から現在臨床現場でよく話に挙がる人材紹介企業や就職説明会など、実際に活用した経験などをもとに、リクルートに関するトラブル、課題およびその対策などについて解説された。
また、本研究会顧問弁護士である姫井葉子先生(春日法律事務所)からは、従業員を採用する際の法的観点からの留意点について解説され、とくに「合意をするなら採用時に」という言葉が印象的であった。そのあと、「獣医学生の就職動向と課題」では、枝村一弥先生(日本大学)が、大学の観点から獣医学生の就職希望地域に偏重がみられること、獣医学生の就職活動が多様化しており職場環境を重視している学生が多いこと、女性の学生が増えているので今後女性獣医師が活躍できる環境の整備が必要であること、小動物臨床における就職活動中のトラブルが増加していることを解説した。その後の「リクルートトラブルを防ぎ定着させるには」をテーマとしたディスカッションでは、質問が枝村先生に集中し、獣医学生がどのような教育を経て臨床現場にやってくるのか、臨床現場との情報の不足、ズレが顕著に感じられる内容であった。
テーマの影響からか、今回はこれまで以上に参加者が集まり、現在の日本の臨床現場における求人および人材確保への意識の高さが感じられた。

会場の様子
(一社)日本獣医皮膚科学会 ひふゼミ2025 開催
2025/10/5
2025年10月5日(日)、朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター(新潟県新潟市)で、(一社)日本獣医皮膚科学会主催による、ひふゼミ2025が開催された。
テーマは「もっと知りたい、内分泌疾患」。前半は世界獣医皮膚科学会から日本の獣医師としてはじめてHugo Schindelka賞を受賞された岩崎利郎先生(ペットの皮膚科、元日本獣医皮膚科学会会長)による講演「犬と猫の内分泌疾患における皮膚症状の特徴 」Part1・2が行われた。続いて(株)キリカン洋行の協賛によるランチョンセミナー「耳スッキリ! 外耳炎を制す洗浄戦略とバイオフィルム」を山岸建太郎先生(本郷どうぶつ病院)が講演された。後半は、どうぶつの総合病院専門医療&救急センター内科主任を務める福島建次郎先生が「内科専門医による内分泌疾患~診断と治療のポイント~甲状腺疾患」「内科専門医による内分泌疾患~診断と治療のポイント~副腎疾患」を講演された。最後は皮膚科医と内科医の総合討論「実はみんなも悩んでいる~内分泌疾患~全員参加型ディスカッション」が実施され、参加者たちは、臨床診療現場で抱えている日頃の疑問や不安について岩崎先生、福島先生に質問していた。
内分泌疾患による皮膚症状、そして内科的な診断・治療について理解が深まるゼミとなった。
なお、次回2026年のひふゼミでは、国際会議「AiANZ with ひふゼミ」が10月9日(金)~11日(日)に奈良県コンベンションセンターで開催される。本会議にはアジア各国から多くの獣医師が集まる。獣医皮膚科学における本学会のさらなる牽引が期待される。
なお、今回のゼミの内容はオンラインにて配信予定。詳細は下記本学会サイトより確認が可能。
https://www.jsvd.jp

岩崎先生の講演の様子

ランチョンセミナーの様子

全員参加型ディスカッションの様子。大嶋有里先生(犬と猫の皮膚科)のファシリテートのもと、当日会場から寄せられた質問に福島先生と岩崎先生が丁寧に回答されていた

新潟大会オーガナイザーを務めた小嶋大亮先生(小島動物病院アニマルウェルネスセンター)。新潟でひふゼミを開催する際はぜひ“内分泌疾患”をテーマに開催したかったと今大会への思いを伝えた

