2025年2月28日(金)、東京都医師会館(東京都・千代田区)にて、(公社)東京都医師会・(公社)東京都獣医師会 合同開催講習会「人と動物のワンヘルス~動物と共に健康寿命を延ばすには~」が開催された。
ワンヘルスは「環境の保全」「人の健康」「動物の健康」を一つの健康ととらえ一体となって守っていく考え方で、様々な研究が報告されている。本講習会ではそれぞれの立場の参加者たちがワンヘルスについて考えるきっかけとなればという考えのもと、3つの講演が実施された。
1題目は「生物多様性保全とワンヘルスアプロ―チ」をテーマに五箇公一先生(〈国研〉国立環境研究所、生物多様性領域室長)により、環境科学の観点から外来生物や感染症の具体例を交え生物多様性保全および持続的社会構築の意義について講演された。2題目は谷口 優先生(〈国研〉国立環境研究所、環境リスク・健康領域主任研究員)による「伴侶動物との生活が人にもたらす健康効果」で、犬や猫といった伴侶動物が高齢者の健康にどのように寄与するか介護や認知症にフォーカスし紹介された。続く3題目の「人と動物が共有できるウェルビーイングを目指して」では西田伸一先生(東京都医師会 理事)から、とくに高齢者の幸福維持のために伴侶動物の果たす役割が大きく期待されること、またフレイルの基準の説明や、今後の介護においてケアマネージャーとともに動物愛護推進員の存在が重要となることなど、その際に人間だけでなく動物の幸せも大切であることを動物の5つの自由(The Five Freedoms for Animal)の解説も交え紹介された。
「人間の自然破壊により野生動物が町中に出没するニュースを目にする機会がふえ、ワンヘルスの重要性を認識する機会が増えました。今回の講義が、医療と獣医療がともにワンヘルスについて考える会になればと期待する」と東京都医師会会長の尾﨑治夫先生はいう。また東京都獣医師会会長の上野弘道先生は「医師と獣医師が連携して伴侶動物を交えたワンヘルスのシステムを構築できれば、獣医師として大変嬉しく思います。ワンヘルスへのアプローチをとおして、すべての人が笑顔で安心して暮らせる社会をつくっていきたい。」という言葉でこの度の講習会を締めくくった。東京都医師会と東京都獣医師会の連携による貢献がますます期待される。

講習会の様子
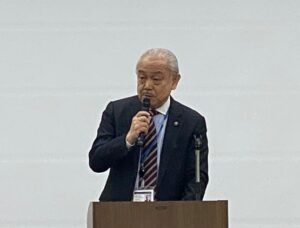
東京都医師会会長 尾﨑治夫先生、開会の挨拶にて

東京都獣医師会会長 上野弘道先生、閉会の挨拶にて



-300x226.jpg)



