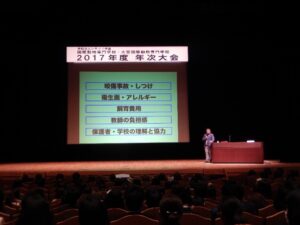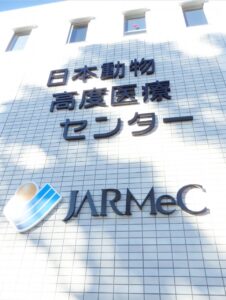2018年5月27日(日)、東京大学農学部弥生講堂一条ホール(東京都・文京区)にて、認定特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会 第21回 公開シンポジウムが開催された。
第21回目を迎える今回は「ペットのストレスサインを見逃すな!」をテーマに展開。武内ゆかり先生(東京大学)からはストレスとは何なのか、そして主に犬に関するストレスのお話しがあり、続く藤井仁美先生(代官山動物病院、自由が丘動物医療センター)は、猫についてのストレス要因を示す表情や行動、ストレスへの対処、飼い主への対応も含め講演された。金巻とも子先生(かねまき・こくぼ空間工房)の「住まい方から考える」では、一級建築士の視点からストレスと住環境、内装素材と音の反射、飼い主と犬猫との空間の取り方の工夫などについて解説され、会場は熱心に耳を傾けた。
人と家庭動物が楽しく暮らすための模索、飼い主の高齢化と高齢動物等、飼い主と家庭動物との現状、そのなかでペットのストレスサインを見逃さないこと、家庭動物たちには野生の時代をあったことを認識し、人間にどのように接してくべきかを考えることは大切、と本協会理事の奥野卓司先生(関西学院大学)。またコーディネーターを務められた西村亮平先生(東京大学)が、未来という概念とストレスとの関係を自身の経験を交え解説され、ストレスはある程度は必要なものである可能性があるのではと、会場に疑問を投げかけられたのが印象的であった。
2007年より内閣府から設立認証を受け、本協会の益々の活躍が期待される。