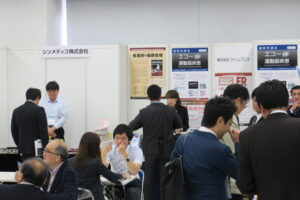2018年6月23日(土)、24日(日)の2日間にわたり、東京都千代田区・秋葉原UDXカンファレンスにおいて、第61回 比較統合医療学会学術大会が開催された。
今回は「総合力」をテーマとし、〈鍼灸セッション〉〈漢方セッション〉〈サプリメントセッション〉の3セッションを設け、それぞれ講演が行われた。1日目の〈鍼灸セッション〉では、獣医鍼灸実施についての発表などのほか、初の試みとして澤村めぐみ先生(沢村獣医科病院)ら、獣医師&鍼灸師によるワークショップが行われ、参加者は興味深そうに意欲的に実習に取り組んでいた。
2日目午前は、教育講演「オゾン療法」6講演が、日本医療・環境オゾン学会の協力により行われた。中室克彦先生(摂南大学名誉教授)による「オゾン療法の基礎」では、人医療におけるオゾン療法の歴史と実績について、三浦敏明先生(北海道大学名誉教授)による「オゾン療法の作用メカニズム」ではオゾン療法の効果の作用機序について具体的に解説された。午後には〈サプリメントセッション〉が(株)イムダインとの共催で行われた。
また、杉本太郎先生(がん・感染症センター都立駒込病院)による特別講演「頭頚部癌に関する最新の話題」や、一般演題では臨床や研究の現場から、さまざまな分野への取り組みが報告された。
動物たちの治療や健康維持のために、幅広い知見や技術を総合的に取り入れていこうとする姿勢を示す学会であった。
学会・セミナーレポート
- 2026年1月 (1)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (7)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (6)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (7)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (4)
- 2025年3月 (7)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (5)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (10)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (5)
- 2024年7月 (4)
- 2024年6月 (3)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (4)
- 2024年3月 (2)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (6)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (5)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (7)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (6)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (3)
第61回 比較統合医療学会学術大会 開催される
2018/6/25
2018年春季合同学会 開催
2018/6/18
2018年6月15(金)~17日(日)、大宮ソニックシティ(埼玉県)にて、2018年春季合同学会が開催された。
今年は、日本獣医麻酔外科学会、日本獣医循環器学会、日本獣医画像診断学会、日本獣医内視鏡外科研究会の4団体が集まり展開。
第96回日本獣医麻酔外科学会では特別シンポジウムとして「国内農水省未承認等の医薬品と医療機器の使用について」(農林水産省)、「犬及び猫における再生医療及び細胞療法の安全性確保に関する指針と届出制度」(枝村一弥先生、日本大学)が実施され、今春策定されたガイドラインを紹介。今年10月1日スタートする届け出にむけて大きく前進した。
第108回日本獣医循環器学会では、海外研究者特別講演として「VALVE Study」(Gerhard Wess先生、ルートヴィヒ・マクシミリアン大学)についての講演が行われ、犬の僧帽弁閉鎖不全症に対する治療薬に関して、熱い議論が交わされた。
第63回日本獣医画像診断学会では3つもの検定講習会が実施され、昨年から参加している日本獣医内視鏡外科研究会は、今年も低侵襲外科の一層の普及を目指し、プログラムを展開した。
さらに今年はジョイント開催として「獣医顎顔面口腔外科研究会」および「日本動物リハビリテーション学会」が加わり学会としての広がりをみせた。また今回は初の試みとして、金・土・日曜日の3日間の開催となり、企業展示も金曜日の午後から実施されることとなった。
参加団体が増え、益々規模が増大し、プログラムの充実が図られる本学会。参加者は思い思いの会場へ足を運び、充実した3日間を過ごした。
認定特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会 第21回 公開シンポジウム 開催
2018/6/12
2018年5月27日(日)、東京大学農学部弥生講堂一条ホール(東京都・文京区)にて、認定特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会 第21回 公開シンポジウムが開催された。
第21回目を迎える今回は「ペットのストレスサインを見逃すな!」をテーマに展開。武内ゆかり先生(東京大学)からはストレスとは何なのか、そして主に犬に関するストレスのお話しがあり、続く藤井仁美先生(代官山動物病院、自由が丘動物医療センター)は、猫についてのストレス要因を示す表情や行動、ストレスへの対処、飼い主への対応も含め講演された。金巻とも子先生(かねまき・こくぼ空間工房)の「住まい方から考える」では、一級建築士の視点からストレスと住環境、内装素材と音の反射、飼い主と犬猫との空間の取り方の工夫などについて解説され、会場は熱心に耳を傾けた。
人と家庭動物が楽しく暮らすための模索、飼い主の高齢化と高齢動物等、飼い主と家庭動物との現状、そのなかでペットのストレスサインを見逃さないこと、家庭動物たちには野生の時代をあったことを認識し、人間にどのように接してくべきかを考えることは大切、と本協会理事の奥野卓司先生(関西学院大学)。またコーディネーターを務められた西村亮平先生(東京大学)が、未来という概念とストレスとの関係を自身の経験を交え解説され、ストレスはある程度は必要なものである可能性があるのではと、会場に疑問を投げかけられたのが印象的であった。
2007年より内閣府から設立認証を受け、本協会の益々の活躍が期待される。